2024年の「IBS研究発表会」は「60周年記念発表会」と題し、当研究所の60周年事業として特別プログラムにて、対面およびリアルタイム配信にて開催しました。ご発表・ご登壇頂きました皆様方、ならびに会場および配信にてご参加頂きました皆様方に、厚く御礼申し上げます。
| 日 時 | 2024年9月20日(金) 10:00~12:30 |
|---|---|
| 会 場 | ベルサール飯田橋駅前 1Fホール |
 会場の様子
会場の様子

IBSが目指す姿 ~これまでの蓄積を踏まえたNEXT STAGEへ~
発表者毛利 雄一(業務執行理事、研究本部長兼企画室長)

特別企画のパネルディスカッションに先立ち、当研究所の毛利業務執行理事より、発表がありました。1964年7月IBS設立の経緯と設立当時の時代背景に始まり、現在に至る当研究所の調査研究業務と社会的ニーズの変貌の関係性、組織内の多様化に対応しつつ、研究活動60年間の歩みが報告されました。また「NEXT STAGE」として、今後の当研究所の調査研究活動、組織運営、研究開発の方針について取組みについて報告されました。


新領域でご活躍の国際比較・空間デザイン・イノベーション・まちづくりなど、多様な分野でご活躍の専門家の4名の方々をお招きし、当研究所代表理事を交えたパネルディスカッションを行いました。
本格的な人口減少時代を迎え、公と民の役割、国と地域の役割の再考、都市や交通のリ・デザイン(再設計、再構築)が求められるなか、これからの政策テーマ、政策集団、そしてそれら課題に対する当研究所を含めたシンクタンクの役割について、クロストークを行いました。
(パネリスト)
市川 宏雄(明治大学 名誉教授 / 帝京大学特任教授)
伊藤 香織(東京理科大学創域理工学部 教授)
森川 博之(東京大学大学院工学系研究科 教授)
中山 靖史(独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)理事)
岸井 隆幸(計量計画研究所 代表理事)
(司会)石神 孝裕(都市地域・環境部門長兼グループマネジャー)
話題提供1 「都市にとっての交通・アクセス」
発表者市川 宏雄(明治大学 名誉教授 / 帝京大学特任教授)

まず有識者の3先生方から話題提供を頂きました。
市川先生からは、都市における交通やアクセス性に着目し、都市の魅力や競争力への寄与について、お話しがありました。国内外の多角的な視点から分析された独自の都市別ランキングを引用しつつ、都市交通とアクセス性が都市の快適性や利便性において大きな役割を果たすとの分析結果をご提示頂きました。
話題提供2 「まちの空間と人」
発表者伊藤 香織(東京理科大学創域理工学部 教授)

伊藤先生からは、都市空間と人の関わり方に焦点を当て、都市の空間デザインや機能性が人々の生活やシビックプライド(市民が持つ都市への誇り)などコミュニティ意識に与える影響について、ご発表いただきました。機能分散と多目的空間の増加が見込まれる今後の都市計画においては、ICT・データを活用した柔軟性のある空間設計が必要であるといったご指摘がありました。
話題提供3 「テトリス型経営とタスク型ダイバーシティ」
発表者森川 博之(東京大学大学院工学系研究科 教授)
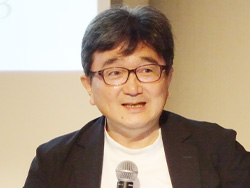
森川先生からは、印象的なスライドや動画も交えて、デジタルエコノミー時代における価値創造と組織運営のアプローチについて、ご解説をいただきました。分野の異なるエキスパートが集まることで、複数の視点からアプローチする「タスク型ダイバーシティ」がイノベーション促進の要素となるとのご指摘のほか、デジタルエコノミーにおける価値創造において協力と共感が組織の発展に不可欠、といったお話しがありました。
パネルディスカッション


学識者からの話題提供を受けて、「都市と交通のクロスロード」をテーマとしたディスカッションを登壇者全員で行いました。
都市と交通の役割やデジタルエコノミー時代の価値創造についての議論に続き、都市の魅力や競争力向上に向けた交通アクセスの役割、シビックプライドの重要性、デジタル時代における価値創造を踏まえた今後の都市のあり方やその発展方法について意見交換されました。また異分野連携やデータ活用が都市計画に不可欠であること、共感性もイノベーションの基盤となることなど、持続可能で快適な都市づくりに向けた計画と分野横断での多角的な視点の融合の必要性が共有されました。
※ 都市計画CPDプログラム認定
土木学会継続教育(CPD)プログラム認定