2年ぶりの開催となるIBS研究発表会は、今年もリアルタイムでの配信を併行して開催いたしました。
お忙しい中、会場および配信にてご参加頂きました皆様方に、厚く御礼申し上げます。
| 日 時 | 2025年7月22日(火) 10:00~12:20 |
|---|---|
| 会 場 | 御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター「Hall WEST」 |
 会場の様子
会場の様子
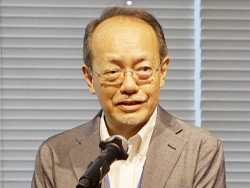
~空間×コミュニティ、2つの視点から~
発表者林 健太郎(都市地域・環境部門 研究員)

近年、ウォーカブル政策は中心市街地を中心に展開されていますが、今後はネイバーフッドにも展開していくことが重要です。ただし、一般的に行政・民間の投資動機が低いネイバーフッドでは、「ウォーカブルな空間の創出」を起点に、まちの魅力向上を図っていく「空間創出型アプローチ」の即座の適用は容易ではないと考えられるため、助走期間として「ウォーカブルな空間」の実現を目指すコミュニティの創出をまずは図っていくような「コミュニティ創出型のアプローチ」が必要です。
本発表では、ネイバーフッドを含む区域全域でのウォーカブル政策の展開を目指して、「コミュニティ創出型のアプローチ」を弊所とともに実践している千代田区の取組みを紹介し、今後のネイバーフッドにおけるウォーカブル都市のあり方について報告しました。
~PTデータ、3D都市モデル活用からの知見~
発表者森尾 淳(都市地域・環境部門 担当部門長兼グループマネジャー)

立地適正化計画の裾野拡大や実効性向上に向けた重要な取組として、データに基づく『まちづくりの健康診断』の取組が進められています。この『まちづくりの健康診断』の高度化の一環として、①都市構造の現状や変化等を空間的に把握する「都市構造評価ツール」の開発、②パーソントリップ調査をはじめとする人流データに基づく都市構造の評価手法の開発を弊所では進めています。
本発表では、都市構造評価ツールの画面構成・機能、評価事例等と、人流データを活用した都市構造の評価指標、評価事例等、具体的に開発した取り組みについて報告しました。
~ヒヤリハット検知や渋滞予測への適用を例に~
発表者宮内 弘太(データサイエンス室 研究員)

近年、AI技術の目覚ましい発達により、建設分野においては生産性向上やコスト削減等を目的に、様々な場面でAI技術が活用されつつあります。国土交通省ではAI技術などの新技術の積極的な活用を推進しています。一方で、交通計画分野においてはAI技術を適用した事例は未だ多くなく、適用することで得られる利点などを広く周知していくことが重要であると考えられます。
本発表では、AI技術を交通計画分野に適用するにあたり、適用することで得られる利点や適用するための進め方などを、当研究所がこれまでに行ってきたAI技術を活用した研究事例であるヒヤリハット検知と渋滞予測を紹介し、今後の交通計画分野におけるAI活用や応用のあり方について報告しました。
~道路交通法改正とゾーン30プラスの新展開、その先へ~
発表者絹田 裕一(交通・社会経済部門 部門長)

「道路交通法施行令の一部を改正する政令」に伴い、来年(2026年(令和8年))9月1日から生活道路を含む小さい道路の法定速度が30km/hに引き下げられます。歩行者の安全を守る上では30km/h遵守を徹底する必要がある一方で、生活道路の法令上の明確な定義が存在しない現状においては、トラフィック機能が必要とされる道路が法定速度の引き下げ対象となる可能性があるなど、求められる道路の機能と現実の運用との間に新たな課題が生じることが危惧されます。
本発表では、道路交通法施行令の改正に伴い、新たに必要性が高まると考えられる技術的政策的な課題を明らかにし、課題解決に向けた対応方針について、報告しました。
※ 都市計画CPDプログラム認定
土木学会継続教育(CPD)プログラム認定