| 日 時 | 2023年6月22日(木)・6月23日(金) |
|---|---|
| 場 所 | コモレ四谷タワーコンファレンス「Room F」 〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 |
| 主 催 | 一般財団法人計量計画研究所 |
| 後 援 | 公益社団法人土木学会、一般社団法人日本モビリティ・マネジメント会議 |
| 協 力 | 国土交通省 |
 MM技術講習会の様子
MM技術講習会の様子
講 師萩原 剛(計量計画研究所)

モビリティマネジメント(MM)は、人々との対話を通して今日の過度なクルマ依存社会から、個人・社会にとって望ましい適度なクルマ利用社会へと変わっていくことを促す取組であることを、自動車利用と健康の観点などから説明いたしました。また、コミュニケーションを中心としたMMの取組は、さまざまな心理要因に直接働きかけを行うことで自発的な変化を促し、長期的な施策の持続効果をもたらし得ることについても説明いたしました。最後に、これらのポイントを押さえたMMの事例として、栃木県小山市の取組を紹介いたしました。
講 師羽佐田 紘之(計量計画研究所)

MMは長期的な取組となることが多いため、「計画」に着目した6つのポイントと6つのテクニックについて説明いたしました。愛知県春日井市などの事例に沿って、目標(ゴール)やコンセプトを定めた上で、データに基づき対象地やペルソナ(具体的な利用者像/非利用者像)を設定することが重要であると紹介いたしました。また、条件を踏まえた適切なスケジュール設定やコミュニケーション手法、効果検証の手法・指標の決定についても紹介いたしました。
講 師水野 杏菜 (計量計画研究所)

行動変容のために、コミュニケーションによりさまざまな心理要因に直接働きかけることが重要であることや、MMに用いられるツールと行動変容の関係性、各ツールの役割と作成時のポイントについて説明いたしました。また、手に取って情報を確認してもらい、日常的に持ち歩いてもらえるよう、ツールをパッケージ化する工夫が有効であることを説明いたしました。
講 師井村 祥太朗(計量計画研究所)

MMを実施した場合(施策群:with)と実施しなかった場合(制御群:without)の比較による施策効果の分析にあたり、直接測定することが難しいwithoutの計測手法について、計測の例を示しながら説明いたしました。また効果計測には、地域全体の変化と個人の変化の2種類があることや、施策目標に応じた評価指標の選定が重要であることを説明しました。
講 師前田 浩成 様(高槻市)

「市民のライフステージに合わせて便利でお得に!」をテーマに、高齢者や障がい者だけでなく、妊娠中の方、乳児、小中学生といった、多様な世代を対象としたバスサービス向上の取組についてご紹介いただきました。ベビーカー同伴時のバスの乗車方法に関する動画を作成し、市の福祉部門のホームページに掲載するといった、公営事業の強みを生かした横連携の取組が紹介され,会場からは大きな関心が寄せられました。
講 師笠間 彩 様(金沢市)

歩行者・自転車・公共交通優先のまちづくりを実践する金沢市のMM事例として、路線バスMMや公共シェアサイクル「まちのり」を用いた大学生向けMMなど、多様な交通モード・世代を対象とした施策をご紹介いただきました。特にシェアサイクルでは、利用者数が25万人を超えたことや、平日と休日の利用の様子から市民と観光客の双方でバランスよく利用されていることが示されました。
講 師大城 博人 様(沖縄県)

沖縄県の公共交通の概況や、国道58号線を中心として実施されている基幹バスシステムについてご説明いただきました。またMMの事例として、沖縄県公共交通活性化推進協議会によるバスに乗りやすい環境整備のための取組や、公共交通の利用を促進させるための広報啓発活動を担う「わった~バス党」が行っている取組についてご紹介いただきました。
講 師藤井 聡 教授(京都大学大学院)

コミュニティバスの運営に成功している自治体の例を挙げて、MMを成功させるための考え方についてお話しいただきました。成功の要因は、公共交通の利用者を増やすという目的を持ち、その目的達成のための合理的な取組を行う「経営」(=マネジメント)の視点を持つことであるとご説明いただきました。前例主義に陥りがちな現状に対して、公共交通の利用を促進するためには明確な意思が必要であるとの心強いお言葉もいただきました。加えて、豊富な事例やデータに基づき、公共交通を利用した場合の利点についてもご紹介いただきました。
講 師松村 暢彦 教授(愛媛大学)・計量計画研究所

松村教授がMM教育の現場で実際に使用しているフードマイレージ※の教材を用いて、ワークショップを行いました。時代(1970年代・2000年代)、居住地(大阪・愛媛)でグループ分けした参加者の方々に、金額などの制約のもと食材を選び、夕食の絵を描いていただきました。この教材は、フードマイレージ及び地産地消への理解を深めるだけでなく、どんな手段で買い物に行くか、何を買うかといった普段の行動が環境や交通の面で社会へ影響を与えていると気づかせることを狙いとしています。
※フードマイレージは、「食品が運ばれてきた距離」×「食品の重さ」で算出される指標です。フードマイレージに交通輸送手段別のCO₂排出係数を掛け合わせることで、輸送の際に排出されたCO₂の試算ができます。
後半は、グループ毎に具体的な地域・状況等を設定し、その地域でMMを実施する場合の悩みについて質疑を行い、松村教授や講師の皆様からアドバイスをいただきました。
講 師松村 暢彦 教授(愛媛大学)

小学校の社会科の授業で習う単元を紹介しながら、MMの定義そのものが社会科教育における多くのテーマと重なり合っていることをご説明いただきました。豊かな暮らしを実現するために、色々な人が同じ方向を向き、言葉を通じて関係を築くことの大切さ、自分の価値観を発信できるMMの楽しさについてもご説明いただきました。
講 師日髙 悟 様(西日本鉄道株式会社)

民間・地域・行政の3者それぞれが抱える課題等を共有・連携しながら進めた取組事例として、AI活用型オンデマンドバス「のるーと」の導入事例を紹介いただきました。自治体がリーダーシップと課題意識を持って施策へ取り組むことや、3者間でコミュニケーションをとりつつ時間をかけて施策を実施することの大切さをお示しいただきました。
講 師水口 旺大 様(国土交通省総合政策局 地域交通課)
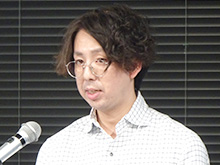
地域公共交通をめぐる現状と共に、地域公共交通活性化再生法の概要や、地域公共交通特定事業の実施状況についてご説明いただきました。また、感染症等によるライフスタイルの変化に対応するべく、交通DX・GX及び他分野共創を通じた「リ・デザイン」を掲げた改正法案や、国が実施するMM施策として「エコ通勤」に関する認証手続き簡略化の取組、MM実施に対する補助制度についてご紹介いただきました。
※ 都市計画CPDプログラム認定
土木学会継続教育(CPD)プログラム認定